日本の高齢化が進み、 介護負担 がますます深刻になっています。
高齢者の割合は増え続ける一方で、介護を必要とする人も年々増加。その背景には「寿命が延びたから」というシンプルな要因だけでなく、「生活環境の変化が高齢者の身体を弱くしてしまったのではないか?」という疑問が浮かびました。
そこで今回は、高齢者の 介護負担 の増加の背景にある「虚弱化」に注目し、予防介護として私たちにできることはないか調べてみました。
介護負担 は増加している
日経の押さえておきたいトップニュース「老いる首都圏、介護が深刻に 4人に1人が65歳以上」
総務省が14日発表した2024年10月時点の人口推計で、首都圏(1都3県)は65歳以上の高齢者が4人に1人を占めた。高齢化で介護需要が高まる一方、職員は足りない。15〜64歳の生産年齢人口が減少するなか、家族の介護負担が膨らめば経済活動の大きな重荷になる。

少子高齢化の進行をすぐに止めることは難しく、医療の進歩によって寿命が延びること自体は良いことです。そのうえで介護負担を減らすには、社会全体でのアプローチが必要になってきます。
- 介護を必要としない体づくり(予防介護)
- 家族・地域での介護支援の充実
- テクノロジーを活用した介護負担の軽減
- 介護職の労働環境を改善する
- 公的支援・社会保障の見直し

個人ができることは①のみ(②~⑤は介護に対する支援であり個人ではどうにもできないので改善について考えられるとしたら①のみ)。
介護負担 増加の要因の1つ、高齢者の「虚弱化」
かつての高齢者は農業や自営業を続ける人が多く、日常的に体を動かしていました。しかし現在は、定年退職後の生活が大きく変化し、身体活動の低下が介護を必要とする期間の延長につながっている可能性があります。
筋肉の減少
昔の高齢者は日常的に動く機会が多かったため、筋力を維持しやすい環境にあったのに対し、現在は運動不足で筋肉が減少した結果、転倒リスクが高まり、介護が必要になるケースが増加しています。
また、昔の食事は野菜中心で栄養バランスが比較的整っていましたが、現在は加工食品の摂取が増え、タンパク質不足や塩分過多が健康に影響を与えていることも懸念されています。
孤立による活動量の低下
かつては地域のつながりが強く、高齢者が社会の一部として活動を続けることができましたが、現代の核家族化によって孤立する高齢者が増え、活動量の低下が介護のリスクを高めている可能性があります。
介護負担 増加させないために、40代から始める介護予防
高齢者の虚弱化を防ぐため、40代の私ができること、どちらかといえば運動音痴の私なので、言い換えれば誰にでもできる予防介護です。
適度な運動習慣を身につける
毎日歩く習慣|どのくらい歩けばいい?
予防介護としての歩行は、最低でも1日30分が目安とされています。歩く前、歩いた後に軽くストレッチをし、ケガのないように気をつけます。
- 推奨歩行時間: 1日30分~1時間(無理なく続けられる範囲でOK)
- 歩数目安: 6000~8000歩(介護予防を意識するなら7000歩以上が理想)
- 歩くスピード: やや速めの歩行(息が少し上がる程度)が筋力維持に効果的
1日の歩行量なので、朝15分+夕方15分のように分けて行っても効果があるそうです。坂道や階段を取り入れると下半身の筋力アップにつながります。
筋力トレーニング|体を支える力を維持するために
筋力維持は下半身の筋肉を鍛えることが特に重要です。加齢により足腰が弱ると転倒リスクが高まり、介護の必要性が増してしまうためです。
週に2~3回の頻度で、最初は無理せず、徐々に負荷を増していく形でのトレーニングが望ましいようです。
- スクワット(太もも・お尻・膝周りの筋力強化)
- 目安: 10回×2セット(無理なくできる範囲で)
- ポイント: 背筋を伸ばし、ゆっくり動くことで膝への負担を軽減
- かかと上げ(ふくらはぎ・バランス力の強化)
- 目安: 15回×2セット(転倒予防に効果的)
- ポイント: 椅子や壁に手を添えて行うと安全
- 太もも上げ(歩行力アップ)
- 目安: 10回×2セット(片足ずつゆっくり)
- ポイント: 腰を伸ばした状態でしっかり膝を持ち上げる
栄養バランスの整った食事
- タンパク質をしっかりとる(筋力維持に重要)
- 塩分・糖分の過剰摂取を避ける
社会とのつながりを持つ
- 家族や友人との関係を維持
- 仕事や趣味を通じて社会参加を続ける
人気の経済ニュース
話題のベストセラー(ビジネス書)
| トーハン調べ 2025年4月8日 | タイトル(リンク先はAmazon Kindle) |
| 1 | 改訂版 本当の自由を手に入れる お金の大学 |
| 2 | 頭のいい人が話す前に考えていること Audible版あり |
| 3 | 嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え Audible版あり |
| 4 | 世界の一流は「休日」に何をしているのか |
| 5 | こうやって頭のなかを言語化する。 Audible版あり(4/11発売) |
| 6 | 人は話し方が9割 Audible版あり |
| 7 | DIE WITH ZERO 人生が豊かになりすぎる究極のルール Audible版あり |
| 8 | 会社四季報 業界地図 2025年版 |
| 9 | 人生は「気分」が10割 最高の一日が一生続く106の習慣 Audible版あり |
| 10 | コンサル時代に教わった 仕事ができる人の当たり前 Audible版あり |





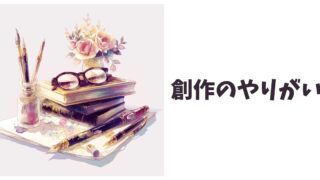














コメント