大型犬。
その姿は堂々としていて、賢くて、頼もしい。
でも――逃げ出したら、話は別だ。
最近、ニュースで「大型犬が脱走」「まだ見つかっていない」という話をよく目にする。
大型犬の脱走の背景にあるのは飼い主側の問題だ。
大型犬の平均寿命は10~15年。
その間に設備も老朽化するだろうが、飼い主だって筋力が落ちるし判断力も低下する。
うちは犬を飼っていない。
でも、子どもがいる。
上の子は犬を怖がっている。
4歳のとき、公園で遊んでいたら、すぐ前の家から脱走してきた小型犬に追いかけられたからだ。
あの犬の飼い主にはまだ怒りを覚える。
「犬に悪気はなかった、ごめんなさいね」ではない。
悪気がないのは分かっている。
だって犬だ。
たまに「犬は悪くない」と責任の所在を犬にする飼い主がいるが、犬のやったことは飼い主の責任だ。
いまは上の子は11歳。
あのときよりも体が大きくなったが、まだ小型でも犬は怖いらしい。
そんな上の子だ。
大型犬を見たら絶対に逃げる。
下の子も、まだ体が小さいから大きな犬を怖がって逃げるだろう。
通学路、公園、近所の道。
もしそこに、制御されていない大型犬が現れたら?
そんな不安が、じわじわと現実味を帯びてきた。
本当に、勘弁してほしい。
犬に噛まれたどうしたらいいのか。
犬に噛まれたらどうする?――大型犬に限らず、即病院へ
犬に噛まれた場合、狂犬病のリスクを含めて速やかに病院を受診することが非常に重要。
なぜすぐ病院に行くべきか?
傷は浅い、出血が5分以内に止まった、意識ははっきしりしている、体調に異常がない場合は救急車を呼ぶ必要はないが、必ず病院に行くこと。
犬にかまれた場合、次のようなリスクがある:
- 狂犬病:発症すれば致死率ほぼ100%。日本では稀だが輸入症例は存在している。
- 破傷風:土壌にいる菌が傷口から侵入し、神経症状を引き起こす可能性あり。
- パスツレラ症・カプノサイトファーガ感染症:犬の口腔内常在菌による重篤な感染症。
自分でいく場合は「外科」または「救急外来」を受診
- 外科系の診療科(一般外科・形成外科・整形外科など)が適している。
- 夜間や休日であれば、救急外来(ER)を受診。
- 傷が浅くても、感染症のリスクが高いため必ず医師の診察を受けるべき。
受診前にできる応急処置の手順
- 流水で5分以上しっかり洗う(石けんがあれば使用)
- 消毒(ただし泡で固まるタイプは避ける)
- 出血がある場合は清潔な布で圧迫止血
- 患部を心臓より高く保つ
落ち着いたら警察に通報する(病院でも可)
他人の犬に噛まれた場合は警察に通報する。
「病院にいるので来てほしい」と伝えれば、警察は必要に応じて来てくれる。
被害の記録を残すためにも、早めの通報と診断書の取得をするべき。
傷の程度が重い、繰り返しの咬傷、子どもが被害に遭ったなど、医師が「事件性がある」と判断した場合は医療機関側から警察に通報することもあるが(医師法第21条に基づく報告義務)、基本的に犬に噛まれた場合は自己申告制。
飼い主が不明でも問題はない。
大型犬 が脱走したときに適応される法令と実例
犬に噛まれたときの対応を知ったところで、次に気になるのは「責任は誰にあるのか?」という点だ。
犬が脱走した場合、人に被害を与えたかどうかによって損害賠償の内容や責任の重さが変わる。
以下に、民法上の原則と実際の判例をもとに整理して説明する。
法的な基本:民法第718条(動物の占有者等の責任)
「動物の占有者は、その動物が他人に損害を加えたときは、損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類および性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。」
これは動物の種類もサイズも関係ない。
飼育されている動物全部が対象内。
脱走した犬が起こしたことについては飼い主が原則として損害賠償責任を負うことになる。
人に被害を与えた場合
損害賠償の対象
- 治療費・通院費
- 慰謝料
- 休業損害・逸失利益(後遺障害が残った場合)
- その他実費(交通費など)
判例①:ドッグラン事故で1600万円の賠償命令(2025年)
- 大型犬(ゴールデンレトリバー)が人に衝突し、肩に後遺障害
- 飼い主が「犬を過信していた」として注意義務違反を認定
- 大阪高裁が約1600万円の賠償命令
判例②:犬が走ってきたのを避けようとして転倒・骨折(2014年)
- 犬に直接噛まれたわけではないが、走ってきた犬を避けた拍子に転倒
- 飼い主は「柵を設置していたが、ロックが外れることを知っていた」
- 「相当の注意をしていたとは言えない」として賠償責任を認定
逃走のみで人に被害がなかった場合
- 人や他の動物に被害がなければ、損害賠償請求は基本的に発生しない。
- ただし、以下のようなケースでは例外的に責任が問われる可能性がある:
例外的に損害が発生するケース
- 他人のペットや家畜に被害を与えた
- 店舗や施設が一時閉鎖されるなど、営業損害が発生した
このような場合、間接的な損害でも因果関係が認められれば賠償責任が生じることがある。
補足:刑事責任の可能性も
- 過失傷害罪(刑法209条)や重過失傷害罪(刑法211条)に問われることもあります
- 地域によっては条例違反(例:特定犬の逃走報告義務)で罰金が科されることも
大型犬 を脱走させない設備が重要
大型犬は徘徊しているだけで恐怖を与えるため、人が噛まれたという被害がなくても周辺の店舗が休業したり学校の送り迎えが必要になったりと“被害”の規模は大きい。
被害が大きければ損害賠償額もかなりなものになるだろう。
動物を飼う上での責任について定められた民法第718条には「ただし、動物の種類および性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。」とある。
つまり、「相当の注意をしていた」と認められれば免責される可能性があるというわけでが、犬の場合は飼育環境や設備の安全管理が最も確認される。
環境相にも犬の飼養管理基準がある。
- 犬の体長・体高に応じて、ケージや運動スペースの広さ・強度が数値で定められている。
- 大型犬の場合は体長の2倍以上の奥行き、体高の2倍以上の高さが必要とされることもある。
大型犬の飼育設備の安全性を確認したい場合、以下のような専門家や機関に相談・依頼するのが適切だと考えられる。
1. 動物病院・獣医師
- 犬の習性や力に基づいた設備のアドバイスが可能。
- 「この犬種ならこの高さの柵が必要」「この素材は噛み壊されやすい」など、実践的な指摘がもらえる。
2. ドッグトレーナー・訓練士
- 脱走リスクのある行動(飛び越え・掘る・噛む)に対する対策を提案してくれる。
- 自宅訪問で環境チェックをしてくれるトレーナーもいる。
3. 動物取扱業の登録者(ペットシッター・ブリーダーなど)
- 環境省の「飼養管理基準」に基づいた設備管理の知識を持っている。
- 特にブリーダーや保護団体の施設管理者は、大型犬の多頭管理に慣れているため、実用的なアドバイスが得られる可能性が高い。
4. 自治体の動物愛護センター・保健所
- 飼育設備の基準や条例に詳しく、相談窓口として機能している。
- たとえば新潟県では秋田犬やシェパードなどの大型犬に対して「特定基準」を設けており、人止め柵や標識の設置が義務付けられている例もある。
5. 建築士・リフォーム業者(ペット対応)
- フェンスや柵、ゲートなどの物理的な設備の強度や構造をチェック・施工。
- ペット対応のリフォーム業者なら、犬の習性に配慮した設計も可能。

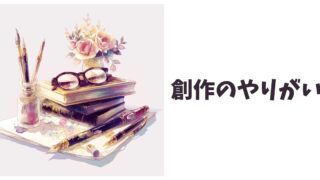















コメント