幼稚園年長児にあたる5~6歳の子どもを対象に、入学直前の秋(10~11月)に「 就学前検診 」というものが行われる。
小学校は義務教育、どうやって始まるのか。
願書の提出や何か手続きが必要なのか。
母親にならなければ一生知ることはなかっただろう。
そして、この 就学前検診 から小学校入学に向けて必要な手続きが始まる。
小学校単位で実施されるので、夏頃に役所から各家庭宛てに検診のお知らせが届くことが多い。
就学前検診 とは?
就学前検診 は、次年度就学する子どもの心身の状態の把握するために行う。
市町村の教育委員会や小学校が実施する。
検診の結果をもとに、教育委員会や小学校は対象の子どもがよい環境で楽しく学習できるように体制を整える。
就学前検診 のあとに就学先が決まる
子どもの就学先は保護者が決める。
義務教育だから「〇〇にいく」は学区で決まるイメージがあったが、子どもの就学先を決める権利は保護者にある。
教育委員会の役割は子どもの教育環境を整えることで、就学前検診 とその後の再検査などを通して「どの学習の場がその子に適切か」という通知を出します。
→ 教育委員会は保護者が就学先を決めるサポート:決定は保護者の役目
就学前検診 は「試験」ではない
就学前検診 は試験ではないので、「当日に〇〇ができなければならない」ということはない。
就学前検診の例
- 知能検査
- 名前をかく
- 手本の線より長い線(短い線)を描く
- 「雨の日に使うもの」など用途に合うものを考える
- 言葉の検査
- 絵に描かれたものの名前をいう
- 絵を見てそれが何か答える)
- 健康診断
- 内科検診
- 歯科検診
- 聴力検査
- 視力検査
就学前検診 |再検査に多い三つの理由
就学前検診のあとに検査結果が届き、再検査が必要な場合は案内に沿って受けるのが一般的。
ここで注意すべきは「再検査」の通知がきたからといって障害があると判断されたわけではないこと。
この結果はあくまでも再検査の知らせ。
もう少し詳しく確認したいというだけなので、普通級への就学についてはこの段階では分からない。
再検査理由はいろいろある。
理由を聞いて「そんなことで?」と驚く保護者も少なくない。
再検査理由1.医師の判断が必要
内科、歯科、聴力、視力の健康面の各検査においては「医師による再検査が必要」だったり、極端に痩せている、肥満傾向である、虫歯があるなど「生活習慣の見直しなど専門家として医師のアドバイスを受けておいたほうがいい」という理由で《再検査》と判断されることがある。
↑
一般的に三歳児検診以降の子どもの発達具合を自治体がチェックする機会がないため、就学前検診は児童の健康の確認の場でもある。当日の検査が保護者不在なので、「保護者も一緒に聞いて欲しい」というケースが意外と多い。
2.当日検査を受けられなかった
就学前検診では子どもたちだけで行動するため、不安や緊張から当日検査を受けられなかった子も少なくない。
再検査の内容は本来の就学前検診で行うことと変わらないものの、マンツーマンでの検査になることが多いため安心して受けられる子どもが多い。
3.発達に関する詳しい検査が必要
検査では結果だけでなく「検査を受けるときの子どもの様子」など総合的な判断が必要になります。
就学前検診 による<行動面の課題>の確認
- 検査を受けられるか
- 一定時間座っていられるか
- 不慣れな場所でも落ち着いて座っていられるか
- 集団行動ができるか(同じグループの子と行動ができるか)
就学前検診 による<理解力>の確認
- 指示にあった行動ができるか
- 問いかけにあった答えができているか
- 年齢相応の受け答えができるか
就学前検診 による<言葉の発達具合>の確認
- 言われた言葉を聞き取る「聴力」はあるか
- 話したいという「欲求」はあるか
- 言われたことを理解する「理解力」はあるか
- 発声するための口周りの「運動能力」はあるか
就学前検診 |再検査の結果が「要観察」だった場合
就学前検診 の再検査の結果が「要観察」の場合、教育委員会・学校・保護者などの関係者が集まって次年度の就学について話し合うことになる。
- 普通学級に在籍するか
- 支援学級に在籍するか
- 学校での学習以外にも通級指導教室に通うのか
集団行動については幼稚園や保育園の先生の話もあるとよいため、事前に幼稚園や保育園に相談して「子どもがどんなことで困っているか?」「どんなときに困った行動が出るのか?」などをヒアリングしておくといい(薦められることも多い)。
話し合いの目的は「子どもにとってより良い学習環境を整えること」。
「より良い」の判断は、子どもがその環境で困ることがない(少ない)が基準になる。
「サポート」を中心にヒアリングすることで、保護者は子どもの就学先を決定しやすくなる。
- 普通学級の場合は、どんな支援が受けられるのか?
- 支援学級ではどんな学習をするのか、どんな支援を受けられるのか?
- 支援学級在籍の場合、普通学級の子どもたちとの交流はあるのか?
- 通級教室を利用する場合の学校の授業との連携は?


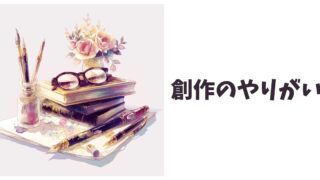





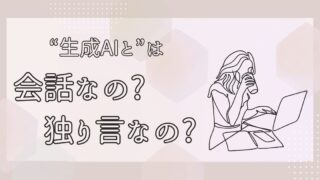







コメント