社会保障改革 について動きがある。
《 社会保障 》と聞くと、年金や生活保護といった“弱者救済”の制度が思い浮かぶ。
だから、健康で働いている現役世代の多くは、「自分にはまだ関係ない」と思っているかもしれない。
実際、私も子どもを産むまで「手当」なんて受け取ったことがなかった。
社会保障はどちらかというと「払うだけ」。
正直、「がっぽり奪っていくな」と思っていた。
でも今ならわかる。
社会保障は、“今の自分”を守るものではなく、“未来の自分”を支える仕組みだということ。
病気になったとき。
職を失ったとき。
子を育てるとき。
――そのすべての場面で、社会保障は私たちの背中を支えてくれる。
今回、石破首相が掲げたのは、この社会保障制度を「今の時代に合ったかたち」に再構築するという試みだ。
注目すべきは、制度の中身をいきなり変えるのではなく、「誰がその議論のテーブルにつくのか」から始めようとしていること。
政党の壁を越え、現場の声を拾い、未来を見据える。
これは、ただの制度改正ではない。
社会という仕組みそのものの再設計だ。
今後も注目したい。
- 【S級】生命や家計の危機に直結する超重要事項
- 【A級】生活に影響を与える情報
- 【B級】今後影響があるかもしれない要監視案件
- 【C級】知識補完
参考
- 首相「社保改革は負担と両面で」参院選後から議論 単独インタビュー|日本経済新聞(https://www.nikkei.com/)
- 首相、社会保障改革へ超党派会議体 立民・野田氏も同調「互いに責任」 令和臨調の会合で|msn(産経新聞)
石破首相の 社会保障改革 のポイント
少子化が加速し、出生数はついに年間70万人を下回った。
医療・介護・年金といった社会保障制度は、現役世代の負担が重く、持続可能性が問われている。
これまでの改革は「政府や一部の政党だけで決められてきた」との批判もあり、石破首相は、より開かれた議論と国民的合意形成を重視する姿勢を打ち出している。
その改革の柱となるのが次の3点。
- 超党派による新たな会議体の設置
- 制度の「持続性」と「負担の公平性」を両立
- 中長期的な財政見通しを担う独立機関の設置
1. 超党派による新たな会議体の設置
- 医療・介護・年金・子育てなど、社会保障全体を対象に議論する場を新設。
- これまでの話し合いは「政府+与党+一部の有識者」が中心
- 野党は国会審議では発言できるが、制度設計の初期段階では関与が薄い
- 与野党の枠を超え、「党利党略を排した議論」ができる体制を目指す。
- これまでの話し合いは政局に左右されやすく、長期的な視点や合意形成が弱かった。
- 医師、介護士、保育士などの現場の担い手や有識者も参加し、制度を使う側・支える側の声を反映。
- これまでの話し合いは医師・介護士・保育士・当事者(高齢者・子育て世代など)の声は間接的
- 話し合いの場(プロセス)をオープンにすることで国民の合意形成を目指す
- これまでの話し合いはパブリックコメントなどはあるが実質的な影響力は限定的で、国民に改革の実感はなく、「また勝手に決められた」「自分たちの声が届いていない」という不信感があった。
2. 制度の「持続性」と「負担の公平性」を両立
- 税制・保険料・給付のあり方を包括的に見直す。特に、現役世代の手取りを増やすための社会保険料の見直しを検討。
- 「改革と負担の両面から議論しなければならない」と明言。
3. 中長期的な財政見通しを担う独立機関の設置
- 政治的なバイアスを排除し、客観的な財政分析と制度設計を行う専門機関の必要性を提起。
- 海外の制度(例:イギリスのOBR、スウェーデンの財政政策評議会)を参考にしつつ、憲法や三権分立との整合性も議論。










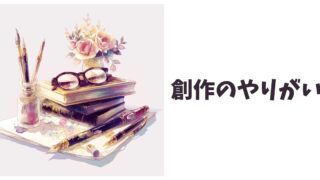





コメント