飲酒運転 は、命を奪う危険性がある重大な違反です。
「お酒を飲んだら運転しない」という当たり前のルールがあるにもかかわらず、飲酒運転 による事故は後を絶ちません。
飲酒運転 には大きく分けて「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があります。
酒気帯び運転は、体内のアルコール濃度によって罰則が変わるのに対し、酒酔い運転は運転が危険だと判断されると、より重い処罰を受ける仕組みになっています。
飲酒運転 の罰則|アルコール濃度で異なる処分
飲酒運転 の罰則は、呼気中のアルコール濃度によって決まります。
0.15mg/L以上になると、酒気帯び運転となり処罰対象になります。
| アルコール濃度 | 処分内容 |
|---|---|
| 0.15mg/L未満 | 処罰なし |
| 0.15mg/L以上0.25mg/L未満 | 免許停止90日間、3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
| 0.25mg/L以上 | 免許取り消し(欠格期間2年間)、3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
「欠格期間」とは、免許取り消し後、一定期間は免許を再取得できない制限です。
飲酒運転 の中でも特に危険な「酒酔い運転」
酒酔い運転は、アルコール濃度ではなく「運転が正常にできないかどうか」で判断されるため、より厳しい処罰が課せられます。
- 免許取り消し(欠格期間3年間)
- 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
酒酔い運転の判断基準
- まっすぐ歩けるか
- 話し方や判断能力の低下があるか
さらに、自動車やバイクだけでなく、自転車の酒酔い運転も違反となります。
飲酒運転 による事故は「危険運転致死傷罪」も適用される
飲酒運転 をして、もし人を死傷させてしまった場合は、「危険運転致死傷罪」が適用されます。
これは、故意に危険な運転をした結果、命を奪った場合に重い刑罰が科されるものです。
飲酒運転 は自分だけでなく、周囲の人々の命を奪う可能性があるため、絶対に避けるべき行為です!
まとめ|飲酒運転 は絶対にしない!
命を守るためにも、絶対に飲酒運転 をしないことが重要です。



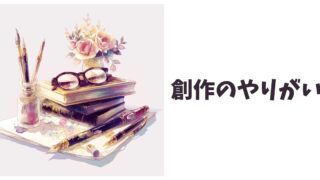












コメント