手に 灰色のベタベタ が……。
始まりは、子どもが幼稚園のイベントで採ってきたサツマイモ。

最初、その 灰色のベタベタ は子どもの手についていた。
うちの子だけではなく、他の子にも。
「手を洗っていないの?」と聞けば、洗っても落ちないとのこと。
土汚れだと思い、家で手を洗ってみたら取れた。
ここで終わっていたら土汚れで終わったが、そのサツマイモを切っていたとき、その 灰色のベタベタ が私の手にも……?
これは一体?
灰色のベタベタ は樹脂配糖体ヤラピンという
灰色のベタベタ は、新鮮なサツマイモを切ったときに出てくる白い乳液が時間が経って変色したもの。
この白い乳液はサツマイモに含まれる「樹脂配糖体ヤラピン(ヤラピノール酸+オリゴ糖)」という物質で、最初は白いが直ぐに黒っぽく変色、ヤニ性でベトベトしている。
時間が経つと松脂(松ヤニ)のように取れにくくなってしまいます。
灰色のベタベタ (ヤラピン)の落とし方
ヤラピンは脂に糖がくっついた樹脂配糖体だから、40℃以上の温水で洗うと落ちやすい。
ヤラピンは酸素系の衣類用漂白剤を使った次の方法で落ちる(塩素系漂白剤は色落ちするので使わない)。
- 浸けこみ時間を長くする
- 浸けこみ温度を40℃以上にする
- 重曹を加える(アルカリ性にすることで漂白力が高まる)
どれか一つでもいいが、二つ、三つ全てを併用することで洗浄力が上がる。
灰色のベタベタ =サツマイモには整腸効果
ヤラピンには腸の動きを促進し、便を柔らかくする働きもある。
だからヤラピン+水溶性食物繊維(ペクチン)の相乗効果で、サツマイモには下痢や便秘に効く整腸作用がある。
さらに、ヤラピンには胃粘膜を保護する作用もある。
サツマイモは漢方では「蕃薯」と言われ、サツマイモを日本に広めるキッカケになったのは青木昆陽の著書は「蕃薯考」という。
いまでこそサツマイモと言われているが、「薩摩地方からきた芋」を意味する“サツマイモ”の呼び名は江戸中期からで、それまでは甘藷・唐芋・蕃薯といわれていた。
サツマイモを食べるとおならが出るのは腸内の異常発酵のせい。
おならを抑えるには、サツマイモを皮付きで食べたほうがいい。
皮付きにしたほうが腸内での異常発酵が抑えられ、おならが出にくくなる。







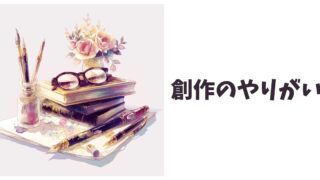








コメント