グッピーを飼育していると、尾びれが細く閉じて力なく泳ぐ――いわゆる「 ハリ病 (針病)」の症状に悩まされることがあり、現在まさに悩んでいる。
この病気は特に稚魚に多く、放置すると数日で全滅することもある危険な症状。
本記事では、実際に発症した際の観察記録をもとに、「ハリ病の原因・対処法・再発を防ぐための工夫」をまとめた。
ハリ病 とは?
- 症状
- 尾びれが閉じて針のように尖る
- 背びれや尻びれも畳みがちになる
- 頭を振るように全身で泳ぐ
- 対象
- 主に生後1週間〜1か月程度の稚魚
- 成魚には「尾びれを畳む」類似症状が出ることもある
- 死亡率
- 非常に高い
- 放置すると数日でほぼ全滅するケースもある
ハリ病 の原因
- 水質悪化:アンモニア・亜硝酸濃度の上昇、pHの不安定など
- 栄養不足:稚魚に適した餌が不足していると発症しやすい
- 遺伝的要因:交配を重ねた系統の虚弱化
- 細菌感染:カラムナリス菌などが関与する場合もある
ハリ病自体は感染しないとされているが、同じ環境下で他の稚魚も発症する可能性が高いため、水槽全体の見直しが重要。
水質悪化の悪化の兆候
グッピーとヤマトヌマエビを同居させている水槽で水質が悪化すると、ヤマトヌマエビの方が先に異常を示すことが多く、グッピーにも特有の兆候(水面でパクパクする、底に沈んで動かない)が現れる。
- エビ類は体表が薄く、アンモニアや重金属の影響を直接受けやすい
- エビ類のほうが酸素要求量が高く、酸欠やpHショックにも弱い
- 脱皮直後は特にデリケートで、水質変化が致命的になる
今回ヤマトヌマエビに異常(動きが鈍くなる・じっとしているなど)がないことから水質悪化は考えにくい。
栄養不足
稚魚に適した餌が不足しているとハリ病を発症しやすい。
グッピーの稚魚には、粒が非常に細かい人工飼料や栄養価の高い生き餌(ブラインシュリンプベビーなど)が適している(稚魚の口は非常に小さいため、サイズと消化吸収のしやすさが重要)。
生まれて~体長1cm未満の場合、生餌なども推奨されているが管理が手間。
乾燥タイプのブラインシュリンプ「アルテミア100」を与えることにした。
体長1cm以上の稚魚にはキョーリンの「ちびっこメダカ・金魚のエサ」を与えることにした。
交配が進んだ系統の特徴と兆候
背骨の湾曲している奇形のグッピーが現在多く、グッピーの交配が進みすぎたと判断することもできる。
同じ遺伝子が繰り返し交配されることで、劣性遺伝子が顕在化しやすくなり水質変化や温度変化に敏感になる(すぐに体調を崩す)。ハリ病や尾ぐされ病などの発症率が高くなる。
F1(1世代目)〜F3程度で新しい血統を入れ、他系統との交配(アウトクロス)で遺伝的多様性を回復させるといい。
「繁殖用」として販売されている個体や、ブリーダーが系統管理している個体を選ぶが理想のようだが、地方都市はそこまで恵まれていないので違うホームセンターのグッピー(オス)を3匹投入して様子をみることにした。
ハリ病 の治療(できること)
- 隔離:発症した稚魚は清潔な水槽に隔離
- 水質改善:水換え・底床掃除・フィルター清掃などで環境を整える
- 塩浴:0.2〜0.5%の塩水浴が有効(例:水1Lに対し粗塩2〜5g)
- 餌の工夫:ブラインシュリンプなど栄養価の高い餌を与える
現在やっている治療は上の4つ。
効果が見られない場合、メチレンブルーやリキッドFゴールドなどの薬浴も検討する(薬浴(メチレンブルーやグリーンFゴールドなど)を魚に使う際、エビには有害な場合がある)。
まとめ
ハリ病は、グッピー飼育で最も多い「稚魚期の急死」の原因のひとつ。
水質・栄養・遺伝・感染、どれも単独でなく複合的に作用して発症するケースが多く見られる。
今回調べて学べたことは――
- 水質が安定していても餌と系統のバランスが重要
- 早期隔離と塩浴で進行を抑えられる可能性がある
遺伝的多様性を意識した繁殖(アウトクロス)や稚魚用の適切な餌の選択が、再発防止の鍵になることを願っている。






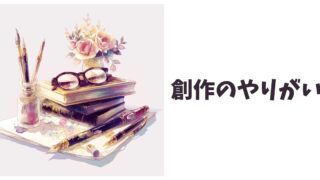










コメント